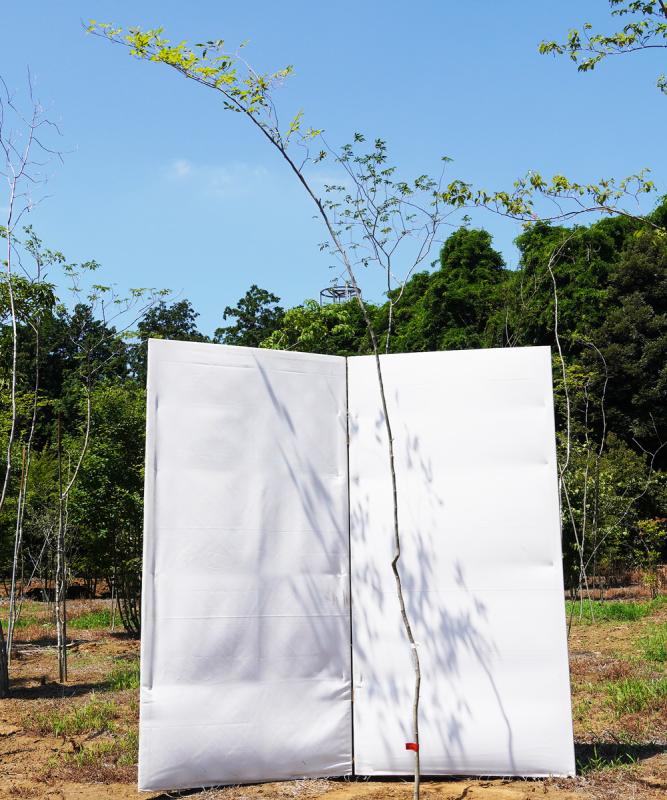【もみじマスターへの道】美しい庭を手に入れるお手入れガイド
美しいもみじを楽しむためのお手入れを学びましょう

四季折々の美しさを楽しむことができる、もみじ。
しかし、その壮大な美しさをお庭で愛でるためには適切なお手入れが必要です。
もし、もみじの管理に困っていらっしゃるようなら、もう大丈夫です。
この記事を読めば、美しいもみじを育てるお手入れの知識を学ぶことができますよ。
もみじの一年を通したお手入れ方法が分かれば、みなさんのもみじも美しく変身しお庭に彩りを添えてくれるはずです。
無理のないお手入れで、美しいもみじを愛でるための第一歩を踏み出しましょう。
この記事は、お忙しい方のために目次の見出しを追うだけでも内容を理解できるようにしています。
詳しく知りたい方は、このまま読み進めていただくか気になる小見出しをクリックしてみてください。
目次
一年を通したもみじの成長と変化

もみじは赤く染まる秋の紅葉だけではなく、四季折々にその美しさを変化させ庭園や景色を魅了します。
初めに、一年を通じたもみじの成長と変化を理解しましょう。

春になると、もみじは新緑の葉を一気に芽吹きます。
この季節は成長と活力の象徴であり、もみじの葉は鮮やかな緑色で庭を彩ってくれますよね。
そして、よく観察すると、5月連休前後に小さな小さな赤い花を見つけることが出来るのですが、みなさん、気付かれていますか。
蝶々が舞っているような姿は、とても可愛らしいです。
春のもみじは、新しい葉が出始めると樹木全体が生気にみちて庭に活気をもたらしてくれます。

夏に入ると、もみじはどんどん生いしげり葉の彩りが濃くなります。
太陽の光を浴び、葉が最も緑色で鮮やかな時期です。
と同時に、近年の温暖化によって葉焼けや枯れてしまうことも多く、この時期は適切な水やりがポイントになってきます。
夏の美しいもみじは、涼しげで庭園に豊かな緑を提供してくれます。
この時期からの水まきが、秋の紅葉の美しさを左右する重要ポイントとも言えるでしょう。

秋になると、もみじの美しい紅葉を楽しむ季節がやってきます。
葉が赤、オレンジ、黄色に変わり、庭園全体が魔法のような景色に変身します。
みなさんのお庭だけでなく、街中や観光地、トレッキングなど、多くの人々がもみじの美しさを楽しむために訪れる季節になりますね。

冬になると、もみじは葉を落として休眠します。
枝のみになりますが、冬の雨で雫が枝にぶら下がる様子は可愛らしいものです。
また、雪に覆われたもみじの枝も幻想的で、庭に静寂と美をもたらします。
もみじ愛好家の方達の中には、枝だけが際立つ冬のもみじを楽しまれる方もいらっしゃるほどです。
春夏秋冬と、もみじは季節ごとに楽しめる落葉高木です。
もみじの魅力を最大限に引き出すためにも、もみじの成長サイクルを理解し季節ごとのお手入れを計画的に行いましょう。
もみじのお手入れスケジュール
-1696215492.jpg)
<春>
剪定:不要な枝や枯れた部分を剪定し樹形を整える。
肥料の施肥:適切な肥料を与え栄養分を補充する。
水まき:土が乾く前に行う。
<夏>
適切な水まき:乾燥を防ぐために適切な方法で水まきを行う。
剪定の継続:成長を調整するために必要なら剪定を行う。
<秋>
落ち葉の掃除:落ち葉を掃除し庭を清潔に保つ。
肥料の追肥:必要に応じて(地植えであれば神経質になることもないです)
適切な水まき:秋以降も気温が高いので引き続き乾燥に気をつける。
<冬>
休眠期間
もみじの肥料と水やり
肥料

もみじは適切な栄養を受けることで、美しい葉と健康な成長を実現します。
肥料は春と秋に施すのが一般的です。
春は成長期の始まりなので、窒素を多めに含む肥料を選びます。
窒素には、葉の緑色を良くする働きがあるからです。
秋は、成長を調整し紅葉を促すためにリン酸とカリウムを多めに含む肥料が適しています。
「葉の春、色付きの秋」という認識で、適切な肥料を選び適量で施肥を行いましょう。
水やり

これまで「もみじは適度な湿度が必要ですが過湿にならないように気をつけましょう。土の表面が乾いたら水を与えるという感じです。」というのが、一般的でした。
しかし、温暖化の影響もあり水やりの常識も変わりつつあります。
与えるタイミングや水やりの仕方によってはダメージを与えることになりかねないので、具体的にお伝えしますね。

もみじの水やりは、近年の連続真夏日を考えたときに春から初秋にかけて「毎日の水やりが理想」です。
「毎日」と聞いて、諦めた方はいませんか。
まだまだ、ここで諦めないでください!
もう少し、読み進めましょう!

水やりのタイミングは、早朝または日没後。
もみじへの効果的で楽な水やり法として、ホースを使って「根元」に水を注ぐという方法を取りいれましょう。
ホースから水がチョロチョロと流れるくらいの水量にして、ホースを「もみじの根元」に置くのです。
そう、ホースを置くだけなのです。
注意点として、水量をマックスにして大量に水を撒いてはいけません。
もみじの周囲に水が流れていくようなら水量が多いということになります。
あくまでも、もみじの根の下にまで水を行き渡らせることが目的なので、水量は周囲に流れていかない水量まで調整してください。
ここは大切なポイントなので、しっかり覚えてくださいね。

水やりをする時間は2時間くらいで大丈夫です。
ホースを置いたままにしておけば、水栓を開け閉めするだけの操作なので楽ですよね。
慣れてくれば、水栓の開け閉めの感覚も覚えてきます。
もちろん、スコールなどで雨水が期待できる日は作業無しで大丈夫です。
わが家は、そのようにして10年間もみじの管理を行っています。

毎日2時間が難しい場合には、1日おきや1時間でも大丈夫です。
全く水やりを行わないことを考えると、もみじにとっては嬉しいお手入れですから。
地植えして数年のもみじは、肥料を忘れたとしても枯れることはありませんが、水やりはもみじの成長に大きな影響をもたらします。
もみじのお手入れは、水やりに意識を向けつつ肥料との正しいバランスを持たせることで、健康な成長と美しい葉を保つことができるのです。
もみじの剪定
剪定の基本ポイント

もみじは落葉した休眠期の冬に剪定するのが基本です。
葉がない時期に枝を整えることで、樹形をコントロールしやすくなります。
不要な枝や枯れた枝以外に、生育が悪かったり交差している枝を剪定します。
また、樹形の内側に向かって伸びている枝は、いずれ交差して風通しが悪くなる原因になるので剪定してスッキリさせましょう。
剪定することで、樹冠内の空間を確保し風通しを良くするので害虫予防にもなります。

また、剪定用具は、ハサミやノコギリなど、みなさんが使い慣れたもので大丈夫ですが、鋭いキレイな刃で剪定することが大切です。
お手入れされていないハサミで剪定してしまうと、カット面が荒くなります。
荒くなることで、感染したり病気になるリスクが高くなるのです。
特に、もみじは繊細なので気をつけましょうね。

意外と見逃しがちなのが、カットの角度です。
意識したことはあるでしょうか。
太い幹などをカットする場合は、水平ではなく斜めにカットしましょう。
切り口が水平だと水がたまり腐敗しやすくなるからです。
また、もみじの太い枝を剪定した場合には、癒合剤を塗って乾燥や雑菌の侵入を防ぎましょう。
もみじの剪定は慎重な作業が必要ですが、正しい手法を実践すれば美しいもみじを育てることができます。
剪定は、もみじの美しさと長寿命をサポートする不可欠な要素なのです。
もみじの病気と害虫管理

もみじの美しい姿を維持するためにも、病気と害虫の管理は欠かせません。
虫が苦手な方もいらっしゃると思いますが、害虫が現れる前に対策をすれば虫を見ることも少なくなります。
正しい害虫対策を知り早期に対処していきましょう。

まずは、正しい植え付けをされているか確認します。
もみじは暴れやすい(どんどん枝が伸びてしまう)ので、自分達が理想とする樹形より大きくなることを想定して、お隣の植栽との距離をとっておくほうが無難です。
適切な間隔がないと密になり、害虫の住処になってしまうからです。
空間があることで十分な空気と日光を確保できるので、もみじにとっても良い環境になります。

しかし、そのような環境でも葉や枝に変色や異常が見られることもあるでしょう。
そのような時は、病気や害虫被害が大きくなる前に早めに対処することで被害を最小限にすることが出来ます。
もみじに多く発生する病気が、うどんこ病です。
発生期間は春から秋という長期間にわたり、特に、梅雨時期は発生頻度が高くなります。
その際には、市販の殺虫殺菌剤を月に1回程度散布してください。
もみじを病気や害虫から守るためには、定期的な点検と早期の対策をおこない、広がらないようにするのが重要です。
もみじの美しさを引き出すお手入れで、最大限に魅力を引き出そう!

もみじがあるお庭は、四季折々の美しさを楽しむための魅力的な場所になります。
一年を通じたお手入れのスケジュールを把握し、正しい剪定や適切な水やりを行うことで、みなさんのお庭のもみじも美しく輝いてくれるでしょう。
もみじを愛でながらお手入れを行うことで、より美しいもみじを堪能しませんか。
関連記事
この記事のライター
九州在住のガーデニングライター
家作りをきっかけに庭管理を始めて12年。
関わってきた時間の分だけ、
植物の声が聞こえるようになりました。
子育てと似ていて上手くいかなかったり癒されたり!
難しく考えないで、
気になった植物に寄り添ってみてくださいね☆彡